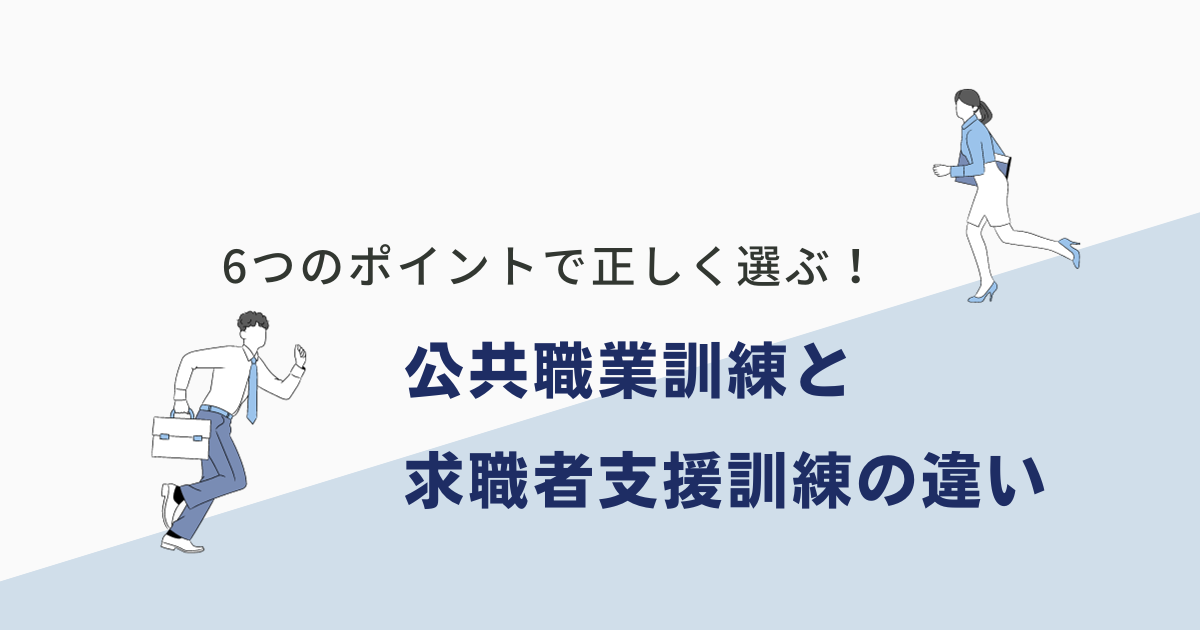はじめに
失業者向けの公共職業訓練と求職者支援訓練は、どう違うのでしょうか。
その制度の目的や仕組みを理解することは、あなたの再就職戦略を最適化する上で極めて重要です。
いまから説明する6つのポイントを知ることで、
を明確に得ることができます。
両者の違いは主に以下の6つのポイントに集約されます。
- コース設定の違い
- 主な受講対象者の違い
- 受講期間の違い
- 給付金の違い(※現在は経済的メリットに差はほぼありません)
- 受講手続きや失業保険の認定の違い
- 開講される可能性の違い
その仕組みや違いはこれから説明していきますが、雇用保険をもらえる、もらえないにかかわらず、あなたは公共職業訓練と求職者支援訓練どちらも受講可能です。
安心して次のステップへ進みましょう!
※この記事は2025年の法改正に対応しています。
※この記事ではハローワークからもらえる給付金の正式名称である「基本手当」を、分かりやすくするために「失業保険」と表現しています。
公共職業訓練と求職者支援訓練の違い

職業訓練は、ハローワークが提供する離職者向けの公共職業訓練と求職者支援訓練の2つに分かれます。
「ハロートレーニング(ハロトレ)」とも呼ばれ、再就職に必要なスキルや資格を無料で提供します。
受講者数は全国で約10万人前後。公共職業訓練の就職率は約8割で、スキル向上や資格取得を通じて再就職支援に大いに貢献しています。
以前は両者で経済的なメリットに大きな違いがありましたが、求職者支援訓練の制度改定により、現在は大きな差はなくなっています。
「給付金はどっちがいいの?」という心配はご無用です!
ただし、受講申込みの手続きなどで細かな違いがあります。
では具体的にみていきましょう。
コース設定の違い
公共職業訓練のコース
公共職業訓練には、職業訓練を専門に行なっている施設内訓練と、都道府県が民間に委託して実施している委託訓練という2つの種類の訓練があります。
主に機械加工、溶接、電気工事士、CADなど、専門性の高いものづくり系のコースが代表的です。
これらの施設は、設備や技術者の育成に特化しています。
パソコン事務、経理事務、医療事務などオフィスワーク系の分野から、FP、介護、建設系、保育などより実務的かつ幅広いジャンルのコースが展開されています。
家事や育児の都合で通学できない方向けに、自宅で受講できるコースも充実しています。

・eラーニング⇒1週間単位の学習カリキュラムを自由な時間に自宅で学習
・オンライン学習⇒受講生が特定の時間帯に自宅でオンライン授業を受ける
という違いがあります。
求職者支援訓練のコース
求職者支援訓練は、失業保険を受給できない人々への雇用支援策として2011年に導入されました。
主な目的は、非正規労働者や長期失業者の再就職支援であり、失業保険を受けられない方を主な対象としています。

公共職業訓練がスキル習得を重視するのに対し、求職者支援訓練は訓練校とハローワークが連携し、求職者の再就職を手厚くサポートすることに重きを置いています。
受講中や訓練終了後の3ヶ月間は、毎月1回、ハローワークで職業相談を受けることが義務づけられます。
ちょっと面倒ですが、再就職への近道です。
パソコン・一般事務、医療事務など公共訓練と重複する分野に加え、トリマーやネイリストなどのよりニッチなコースも提供されています。
基礎コース(2〜4か月:就職に関する基本的な知識とスキル)と実践コース(3〜6か月:専門的なスキル)の2つに分かれ、大半は実践コースです。
公共訓練よりもeラーニングやオンライン学習のコースが充実しています(WEBデザイン、プログラミング、英会話など)。
通常は1年間の間隔が必要な職業訓練ですが、求職者支援訓練の基礎コースを受けた後、すぐに実践コースを受講できる特例があります。
資格やスキルを身につけるという点では公共職業訓練と同じですが、求職者支援訓練では求職者の再就職を訓練校とハローワークで手厚くサポートしていくことに重きを置いています。

訓練受講中や訓練終了後の3ヶ月間は、毎月1回、ハローワークに来所し職業相談を受けることが義務づけられます。
また、自宅で受講できるeラーニング学習やオンライン学習のコースが公共職業訓練よりも充実しており、内容はWEBデザインやプログラミング、観光、英会話、パソコン、医療事務などといったコースが用意されています。
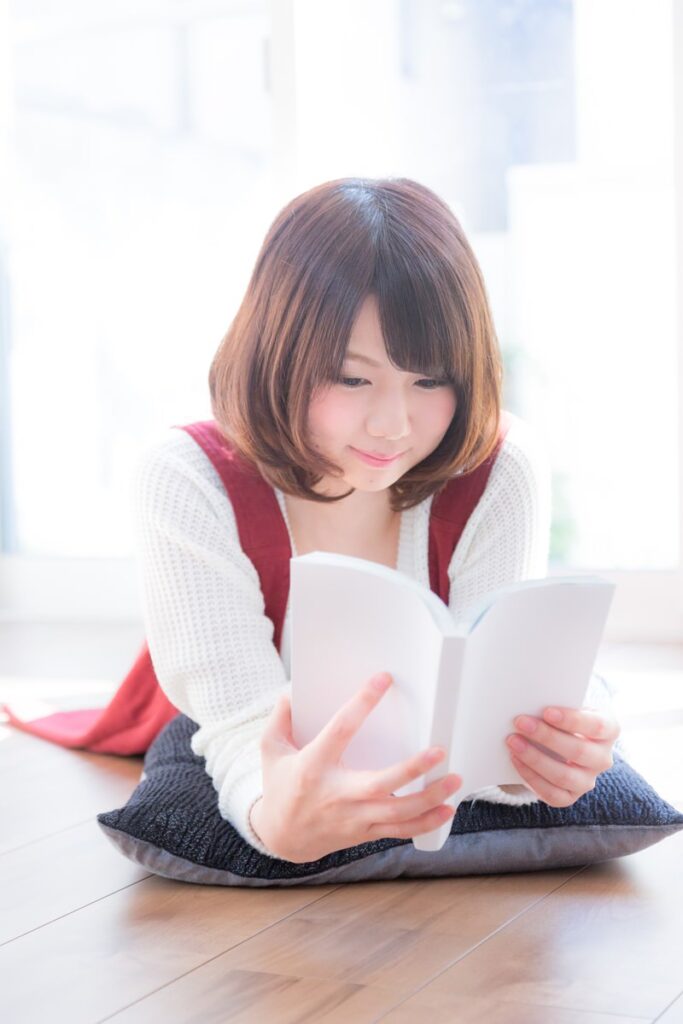
主な受講対象者の違い
両訓練の対象者に根本的な違いはありませんが、制度設立の背景から「主な対象者」には明確な区別があります。
| 訓練の種類 | 主な受講対象者 | 備考 |
|---|---|---|
| 公共職業訓練 | 失業保険を受給している求職者 | 制度設計上、失業保険受給者の早期再就職を促進する役割を持つ。 |
| 求職者支援訓練 | 失業保険を受けられない求職者 | 失業保険の適用がない離職者、フリーランス、失業保険受給終了者などが中心。 |

失業保険を受けている人も受けていない人も、公共職業訓練あるいは求職者支援訓練どちらも受講することができます。 安心してください!
※ただし、「介護労働講習」のみ、後述の受講指示でないと受講できません。
受講期間の違い
受講期間はコースの目的によって大きく異なります。
特に公共職業訓練には、キャリアチェンジを強力にサポートする長期コースが存在します。
| 訓練の種類 | 主な期間 | 特徴的なコース |
|---|---|---|
| 公共職業訓練 (主に雇用保険受給者向け) |
3ヶ月〜7ヶ月が中心。 最長2年間。 |
長期人材育成コース (1年〜2年): 保育士、介護福祉士などの**国家資格**取得、学歴(短大・専門卒)取得が可能。 授業料免除。(※ただし、テキスト代等は自己負担の場合あり。) |
| 求職者支援訓練 (主に雇用保険を受給できない方向け) |
2ヶ月〜6ヶ月が中心。 最短2週間。 |
**基礎コース**(2ヶ月〜4ヶ月)や、1日3時間程度の**短時間コース**が存在。 **オンライン学習**(eラーニング)が比較的充実しており、Webデザイン、プログラミング、事務スキルなどが多い。 |


失業保険をもらえる方は、長期人材育成コースのような長期間の訓練でも、在学期間中に失業保険や交通費が支給されるため、財布の心配なく訓練に集中できます。
さらに入学金はもちろん授業料も免除されることから大変魅力的なコースといえますね。
給付金・失業保険延長:経済的支援の現状(2025年改正対応)
数年前に求職者支援訓練の制度が改定されたことにより、現在では公共職業訓練と求職者支援訓練の間で、経済的支援の面に大きな差はなくなっています。
訓練を選択する上で、給付金に関する心配はほとんど不要です。
訓練を「受講指示」で受ける場合、以下の絶大な経済的支援が適用されます。
【具体的な事例:給付金延長のメリット】
Aさんは自己都合退職後、失業保険の給付日数が残り30日となりました。
しかし、この状態で6ヶ月間の公共職業訓練を「受講指示」で受けた場合、残りの30日だけでなく、訓練終了までの約180日分、つまり実質5ヶ月分の失業保険が延長されて支給されます。
これにより、金銭的な不安なく安心してスキル習得に集中できるわけです。

経済的な不安なく訓練に集中できるということですね。

これらの経済的なメリットをがっちり得るためには、職業訓練を「受講指示」で受けるかどうかがとても重要なポイントになります! これを逃す手はありません!
【受講指示で受ける条件】
訓練開始の前日に失業保険の残り日数が一定数あることが必要です。
詳しくは魅力いっぱいの職業訓練だがメリットとデメリットを見極めよう!で説明しています。

要するに、訓練の受講を開始するときに失業保険の支給日数がある程度残っている事が必要なんですね。
失業保険非受給者への支援内容
失業保険をもらい切った方や、そもそも失業保険がもらえない方などには「職業訓練受講給付金」という制度があります。
受給要件に該当すれば、月額10万円と交通費が訓練期間中、受給できます。
【具体的な事例:非受給者への支援】
Bさんは個人事業主を廃業したため、失業保険の受給資格がありませんでした。
Bさんが4ヶ月間のWEBデザインの求職者支援訓練を受け、要件を満たした場合、訓練期間中、毎月10万円と交通費が支給されます。
これは、生活費の心配を軽減し、異業種へのキャリアチェンジに集中できる大きな助けとなります。

職業訓練受講給付金は、求職者支援訓練の受講生だけでなく、公共職業訓練の受講生どちらも利用できます。みんな平等です!
受講手続きや失業保険の認定の違い
失業保険の認定手続きにおける「手間」に大きな違いがあります。
これは日々の訓練に集中できるかどうかに関わるため、重要な比較ポイントです。
| 項目 | 公共職業訓練 | 求職者支援訓練 |
|---|---|---|
| 応募書類提出先 | ハローワークへ提出(ハローワークが訓練校に提出を代行) |
ハローワークと訓練校の 両方に自分で提出が必要 |
| 認定手続き代行 (受講指示の場合) |
訓練校が代行(受講生はハローワークに行く必要なし) | 訓練校による代行は**なし** |
| ハローワーク来所義務 (給付金受給者) |
受講指示なら**不要**。 受講指示ではない場合は、月1回訓練後に来所。 |
**月1回**、ハローワークへの来所(職業相談・認定手続き)が義務。 |

受講指示で公共職業訓練を受けると、訓練校が失業保険の手続きを全部やってくれるので、訓練期間中はハローワークに行かなくていいのは大きな違いです! 楽チンですね!
開講される可能性の違い
| 訓練の種類 | 開講可能性の基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 公共職業訓練 |
施設内訓練(ポリテクセンター等)は 定員割れでも開講されることが多い。 委託訓練は応募人数次第で 不開講となることがある。 |
国や自治体が直接運営する施設内訓練は、公共サービスの観点から開講しやすい。 委託訓練は、求職者支援訓練と同様に応募人数が少ないと中止になる場合がある。 |
| 求職者支援訓練 | 開講されないことがある。 | 民間委託であり、運営コストの観点から、応募人数が募集定員の半分以上にならないと開講前に中止されることが多い。 |

せっかく職業訓練を申し込んだのに受講できない場合もあるんですね
結論:公共職業訓練と求職者支援訓練どちらを選ぶべきか?
受講者が失業保険の対象であるかどうかに関わらず、公共職業訓練と求職者支援訓練のどちらも利用可能で、さらに経済的なメリットも遜色ありません。
そのため、どちらの訓練を選ぶかの判断基準は、「失業保険の有無」から「コースの内容」へと完全にシフトしました。
最も重要なのは以下の2点に絞られます。

迷うのはもう終わり!
訓練コース選択においては、公共職業訓練と求職者支援訓練の両方から受講したいコースを広く調査し、最もあなたの希望と就職に役立つコースを選びましょう。
訓練が実際に開講されるかどうかは、運営主体によって判断基準が異なります。
訓練選びを終えたら、次は選考対策です。さあ、次のステップへ一緒に進みましょう!
関連記事:次のステップへ─行動の証拠で合格率を劇的に上げる方法
いよいよ合格準備の最終段階。 訓練選考で重視されるのは「知識」より「行動の証拠」。 履歴書や志望動機を自動で整えられる無料ツールを使い、面接対策を最短で仕上げましょう。
【今すぐ使える無料ツール】合格を引き寄せる準備はこちら職業訓練Q&A
- Q複数の職業訓練を同時に申し込むことはできますか?
- A
いいえ、同時に複数の訓練を申し込むことはできません。一度に一つのコースしか選択できません。ただし、申し込んだコースが不合格になったり開講されなかった場合は、その時点で他の訓練に申し込むことができます。
- Q失業保険をもらいながら職業訓練を受ける場合も、認定日と認定日の間に2回以上の求職活動は求められますか?
- A
職業訓練を受けている間は、求職活動が必要ありません。これは公共職業訓練と求職者支援訓練の両方に適用されます。
- Q訓練プログラムの受講資格に年齢制限や学歴要件はありますか?
- A
企業実習付きの訓練では、一部で55歳以下の年齢制限がある場合があります。
しかし、多くの職業訓練には年齢制限はなく、学歴要件もほとんどのコースで必要ありません。
ただし、例外として長期人材育成コースでは、短大、専門学校への入学となるため高校卒以上の学歴が必要です。