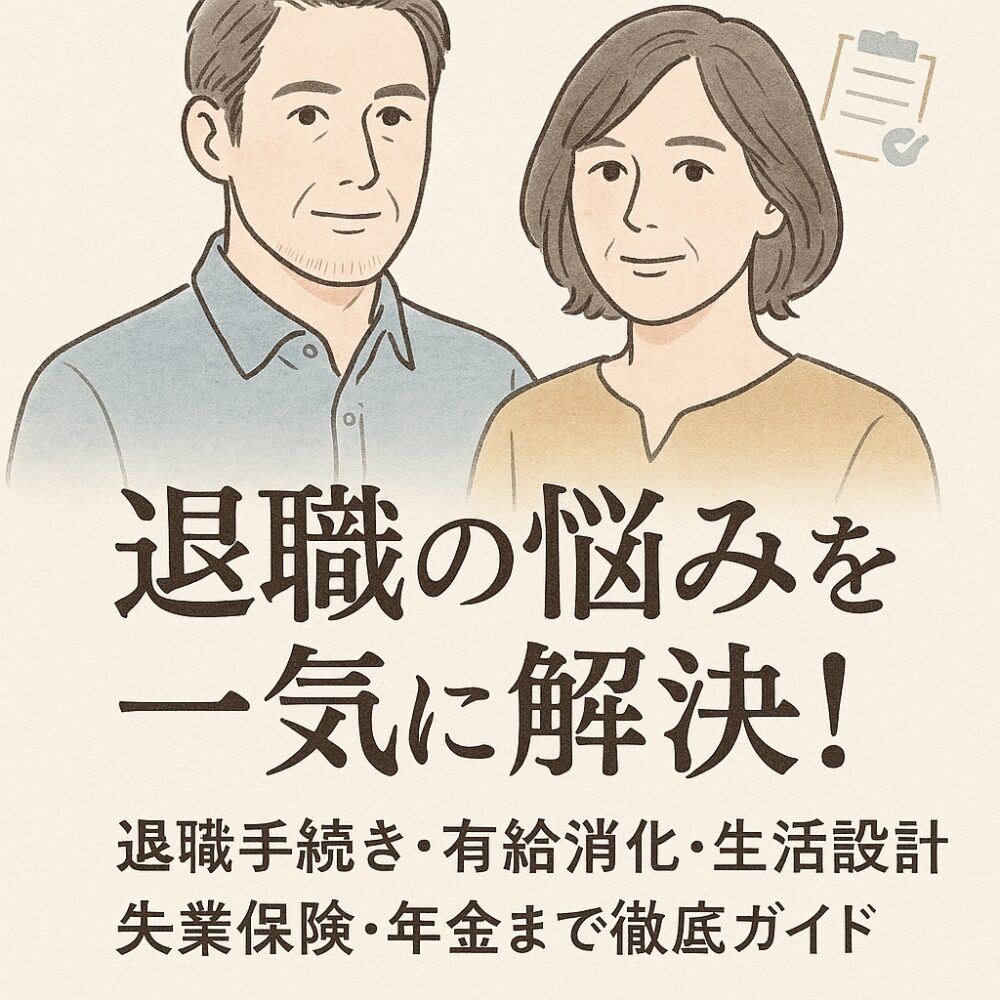はじめに
退職や転職を考えるとき、多くの人がこんな悩みを抱えます。
本記事では、退職を検討し始めてから、手続き・生活の備え・再スタートまでを網羅。
不安を手放せる情報を丁寧に解説します。
退職を考えたとき、まず整理したいこと
退職を考えるきっかけ

長年勤めた会社を辞めるのは、人生の大きな転機。不安を感じるのは当然です。
退職理由を整理する
「なぜ辞めたいのか」「何を変えたいのか」を紙に書き出してみると、頭の中が整理しやすくなります。
それが本当に転職でしか解決できないことなのか、今の職場でも改善できることなのか、冷静に見つめ直すことが大切です。
「退職=逃げ」ではありません。より良い環境を選ぶのは前向きな選択です。
退職の流れ
退職を決意したら、以下の流れで手続きを進めていくとスムーズです。

法的には2週間ルールが優先ですが、引き継ぎや人間関係を考えると早めの相談が良いでしょう。
退職の法的ルールと注意点
| 雇用形態 | 法律上のルール | 就業規則のルール | 実務上のポイント |
|---|---|---|---|
| 正社員(無期雇用) | 民法627条により2週間前の申し出で退職可能 | 多くは「1ヶ月前」「2ヶ月前」など長めの申告期間あり | 法的には2週間ルールが優先だが、円満退職や引き継ぎのため早めの相談が望ましい |
| 契約社員 |
原則として契約期間満了まで勤務 やむを得ない事情で契約途中退職可能(民法628条) 5年超勤務で無期契約へ転換可能(無期転換ルール) |
退職申し出は一般的に「1ヶ月前」程度がマナー | 契約途中の自己都合退職は原則不可。特別な理由があれば証拠を準備し相談 契約更新や退職のタイミングを把握することが重要 |
| 派遣社員 |
契約期間満了まで勤務が原則 やむを得ない事情で途中退職可能(契約社員同様のルール適用) |
派遣先・派遣元双方への連絡や調整が必要 | 契約内容や就業規則を確認し、理由がある場合は早めに双方に相談 |
| パート・アルバイト |
無期契約なら民法627条に基づく2週間前の申し出で退職可能 ほとんどは期間を決める有期契約で、契約期間中は原則勤務 契約書が交わされていない場合や、契約内容と実態が異なるケースもある |
会社の規定に従うことが多い(契約書や就業規則で詳細規定) | 契約書・就業規則の確認を必ずし、違和感があれば労働相談を利用 急な退職は避け、できるだけ早めの相談とシフト調整に協力すること |
退職ルールと円満退職のコツ(雇用形態別)
正社員の退職ルールとポイント
契約社員・派遣社員の退職ルールとポイント
契約社員や派遣社員は期間限定の契約です。契約途中での自己都合退職は特別な事情がないと認められず、契約更新しない旨は1ヶ月前に伝えます。長期で更新を繰り返すと無期契約に切り替えられ、より安定した働き方ができます。
パート・アルバイトの退職ルールとポイント
アルバイトも契約を結びますが、短期やシフト制のため、契約書自体が交わされていなかったり、契約内容と実際の勤務時間や日数が合わないこともあります。
このような実態と制度のズレから「契約を結んでいる実感が薄い」という違和感が生じています。
法律では契約書の交付は義務ですが、運用が追いついていない職場もあります。
労働者は契約内容を確認し、不明点は積極的に確認・相談しましょう。

労働基準監督署への事前相談は、会社との交渉を有利に進めるうえで効果的です。会社は監督署による指導や調査を避けたい心理があり、相談だけで対応が改善されることも多いため、トラブル回避に役立ちます。
引き継ぎ書の詳細例
引き継ぎ書は、担当業務や顧客情報、進行中の案件、注意点、今後の対応方針まで具体的に記載することが大切です。
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 担当業務 | 法人営業(新規開拓・既存顧客フォロー)、見積・受発注管理、展示会運営 |
| 顧客リスト |
|
| 案件進捗 |
|
| 注意点 |
|
| 今後の対応 |
|
| 取引先挨拶 | 6/15~6/20に主要顧客へ退職挨拶メール送付予定です |
| 社内連絡先 | 総務:山田(内線123)、経理:佐藤(内線124) |