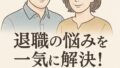退職日は、たった1日の違いで社会保険料の負担が大きく変わり、最終的な手取り額に直結します。
特に、次のステップとして職業訓練や再就職活動を控えている方にとって、無駄な支出を抑えることは非常に重要です。
この記事では、社会保険料を最大限節約し、次のステップへスムーズに移行するための、最適な退職日選びの仕組みと具体的な方法を徹底解説します。
退職は人生の大きな転機。せっかくなら、少しでも損をせず、気持ちよく新しい一歩を踏み出したいですよね。
この記事では、社会保険料の仕組みや退職日選びのポイントを、ケース別の最適解とともに分かりやすく解説します。
わずか1日の違いで社会保険料が1ヶ月分変わる仕組み
まず、なぜ退職日によって社会保険料(健康保険・厚生年金)の負担が変わるのか、その仕組みを押さえておきましょう。
まず、社会保険料の控除は日割り計算ではなく、月の末日に在籍しているかどうかで決まります。
このルールのため、退職日が「月末」か「月末の1日前」かで資格喪失日が変わり、支払う会社の社会保険料(健康保険・厚生年金)の月数が変わります。
| パターン | 退職日 | 資格喪失日 | 会社の保険料支払い対象 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 月末退職 | 9月30日 | 10月1日 | 9月分まで必要 | 9月分の保険料も会社と折半で負担。最後の給与で2ヶ月分引かれ、手取りが減る可能性が高い。 |
| 月末1日前退職 | 9月29日 | 9月30日 | 8月分まででOK | 9月分の会社の社会保険料(労使折半分)が免除! |

退職は、会社によっては最後の給与で「前月分+当月分」の2ヶ月分の保険料がまとめて控除され、一時的に手取りが大幅に減る場合があります。
手取りの急激な減少を避けたいなら、月末の1日前に退職することが基本戦略となります。
再就職先が翌月1日入社の場合、月末1日前退職(例:9月29日退職、10月1日入社)が最もお得になります。
「月末1日前退職」がお得な理由を徹底解説
多くの人が、「新会社でも結局10月分の保険料は引かれるから同じでは?」と考えがちですが、そうではありません。
お得になる鍵は、「退職月(9月)の保険料負担がなくなる」点と、「国民年金・国民健康保険の全額負担を回避できる」点にあります。
| 比較項目 | 月末1日前退職(9/29) 10/1入社 | 月末退職(9/30) 10/1入社 |
|---|---|---|
| 9月分の保険料負担 | なし(旧会社・新会社とも) | あり(旧会社で労使折半を負担) |
| 10月分の保険料負担 | あり(新会社で負担) | あり(新会社で負担) |
| 退職後の国保・国年負担 | なし(10/1に新会社加入のため) | なし(10/1に新会社加入のため) |
| 結論 | 1ヶ月分の社会保険料が節約できる! | 1ヶ月分の保険料が余分にかかる |
1ヶ月分の社会保険料(労使折半)の自己負担分がまるまる節約できるため、「月末1日前退職」がお得になるという結論になります。
💰 退職日による支出損得シミュレーション
月末退職の「2ヶ月分控除」や、厚生年金加入期間の影響を含めた比較を行います。
入力項目
🔍 シミュレーション結果
ご利用上の重要な注意点
- 住民税・雇用保険は本シミュレーションに含まれていません。
- 国民健康保険料は自治体や前年の所得・資産により算出が複雑です。必ず市役所で試算し、任意継続と比較してください。
- 月末退職を選ぶと、最後の給与で前月分+当月分の社会保険料が控除されます。本システムは通常手取りと比較して警告表示します。
- 厚生年金の加入期間が短くなると、将来受取る年金額が減少する可能性があります。
- 本ツールは簡易試算です。最終的な手取り額・保険料は会社の給与計算担当・各保険組合・自治体へご確認ください。
再就職まで期間が空く場合の年金・健康保険の負担
職業訓練を受けるなどで再就職まで期間が空く場合は、月末1日前退職で会社の社会保険料は節約できますが、その代わりに国民年金と国民健康保険の全額自己負担が始まります。
1. 国民年金保険料の負担(全額自己負担)
月末1日前に退職(例:9月29日退職)すると、9月分の厚生年金保険料は発生しませんが、9月分の国民年金保険料(2025年度:月額17,510円 日本年金機構より)が発生し、全額自己負担となります。
| 保険の種類 | 月末退職(9/30)の9月分負担 | 月末1日前退職(9/29)の9月分負担 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 会社の保険料(約半分) | 国民健康保険/任意継続(全額) |
| 厚生年金 | 会社の保険料(約半分) | 発生なし |
| 国民年金 | 発生なし | 発生(全額:約1.7万円) |
2. 国民健康保険 vs 任意継続(費用比較が最重要)
健康保険料の全額自己負担額は、年金以上に高額になりやすいため、必ず安い方を選びましょう。
| 比較項目 | 国民健康保険(国保) | 任意継続 |
|---|---|---|
| 保険料計算 | 前年の所得、家族構成、自治体の料率で決まる(高額になる可能性大) | 退職時の標準報酬月額に基づく(上限あり) |
| 加入期間 | 制限なし | 最長2年間 |
| 給与が高い場合 | 任意継続の上限額より国保料が高額になる場合があるため、任意継続が得になるケースも多い。 | – |
健康保険料は全額自己負担になると高額になりがちです。
退職日が決まったら、すぐに「国民健康保険」と「任意継続」の両方を試算し、安い方を選ぶのが鉄則です。
任意継続保険料と国民健康保険料の違い・調べ方
任意継続保険料の調べ方
計算方法
退職時の「標準報酬月額」または、健康保険組合・協会けんぽの「全被保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い方に保険料率をかけて計算します。
報酬額(標準報酬月額)に上限が設定されており(例:協会けんぽは32万円など)、退職時の標準報酬月額が上限を超えていても、上限額までしか保険料の計算対象になりません。
支払い方法
会社負担がなくなり全額自己負担となるため、在職時の約2倍の金額になることが多いです。
加入した月から支払いが始まり、2年間継続できます。
以前は2年間の加入が義務付けられていましたが、今は途中で脱退することができます。
退職後の次の年に国民健康保険料が安くなることがあるので、2年を待たずに途中で任意継続から国民健康保険に切り替えることも検討したいところです。
国民健康保険料の調べ方
計算方法
前年の所得や家族構成、年齢、居住地によって金額が異なります。
医療分・支援分・介護分(40歳~64歳のみ)を合算し、自治体ごとに計算されます。
自治体の窓口でも試算を出してくれます。
給与が高い場合のポイント
任意継続保険料は標準報酬月額の上限(例:協会けんぽは32万円など)までしか計算されません。
そのため、国民健康保険料よりも任意継続保険料の方が安くなるケースがあります。
例:月収80万円(年収960万円)の場合、国民健康保険料は月額6.8万円程度になることもありますが、任意継続保険料は上限(例:32万円)に基づいて月額3万円台となるため、任意継続の方が安くなる。
健康保険組合によって上限額は異なるため、必ず最新の情報を確認してください。
協会けんぽのホームページ
保険料率や最新情報、任意継続に関する詳細も掲載されています。
厚生年金保険料は、退職後は原則として支払い義務がなくなります。
ただし、退職時点で60歳未満の場合、国民年金に加入し、国民年金保険料を支払う必要があります。
※国民年金保険料は2025年度で月額1万7510円、2026年度は1万7920円となり、全額自己負担となります。
知っておきたい!退職日調整で失敗しないための重要チェックリスト
退職日を調整する際には、以下の実務的なリスクを回避することが、スムーズな再就職準備に不可欠です。
1. 賞与・退職金の支給条件を絶対確認!
ボーナスや退職金は「支給日在籍要件」(支給日に在籍していること)が条件になっている場合があります。
- Q賞与(ボーナス)と社会保険料の控除はどうなる?
- A
退職月に賞与が支給される場合、その賞与に対して社会保険料がかかるかどうかは、賞与の支給日と資格喪失日(=退職日の翌日)の関係によって異なります。
- 支給日が資格喪失日(退職日の翌日)より前の場合:
その賞与は「在職中」とみなされ、社会保険料が控除されます。 - 支給日が資格喪失日以降の場合:
その賞与は「退職後」とみなされ、社会保険料は控除されません。
- 支給日が資格喪失日(退職日の翌日)より前の場合:
2. 雇用保険(失業給付)の手続きを遅らせない
職業訓練の受講が決まると、雇用保険(失業給付)の給付制限が解除されるメリットがあります。退職後は速やかにハローワークでの手続きを始められるよう準備が必要です。
◉必要書類:
会社から発行される「雇用保険被保険者離職票1・2」など。退職時に忘れずに受け取るよう依頼しましょう。
発行には、おおよそ2週間程度かかります。
◉訓練希望者向け:
職業訓練の受講開始日と給付開始日を意識し、退職日を調整、あるいは雇用保険の手続き日を調整することで、失業手当を無駄なく受け取ることができます。
3. 健康保険の「空白期間」は絶対避ける!
健康保険に加入する義務があるため、「空白期間には保険を使わない」という考え方はリスクがあります。
未加入期間中の予期せぬ医療費は全額自己負担となり、後日、未納期間の保険料を遡及して請求される可能性もあります。

企業との退職交渉や手続きに不安がある場合は、退職代行サービスの利用も一つの選択肢です。
弁護士法人や労働組合が運営するサービスを選べば、法的な問題も安心して任せられます。
まとめ:あなたの最適な退職日とアクションプラン
| あなたの状況 | 最適な退職日の結論 | 最優先で取るべきアクション |
|---|---|---|
| 再就職先が決まっている(入社日月初) | 月末の1日前退職 | 賞与・退職金の支給日を確認し、入社日との空白期間がないよう調整する。最もお得なパターン! |
| 退職後すぐに扶養に入る | 月末の1日前退職 | 配偶者の会社に扶養の条件と手続きを事前に確認する。 |
| 社会保険料の節約を最優先 | 月末の1日前退職 | 退職後の国保と任意継続の保険料を試算し、安い方を選択する。 |
| 再就職まで期間が空き職業訓練を検討 | 月末の1日前退職 | 浮いた資金を生活費に充当し、速やかにハローワークで手続きを行う。 |
賢い退職日選びで節約した資金を、充実した職業訓練や再就職活動に活かしましょう!